

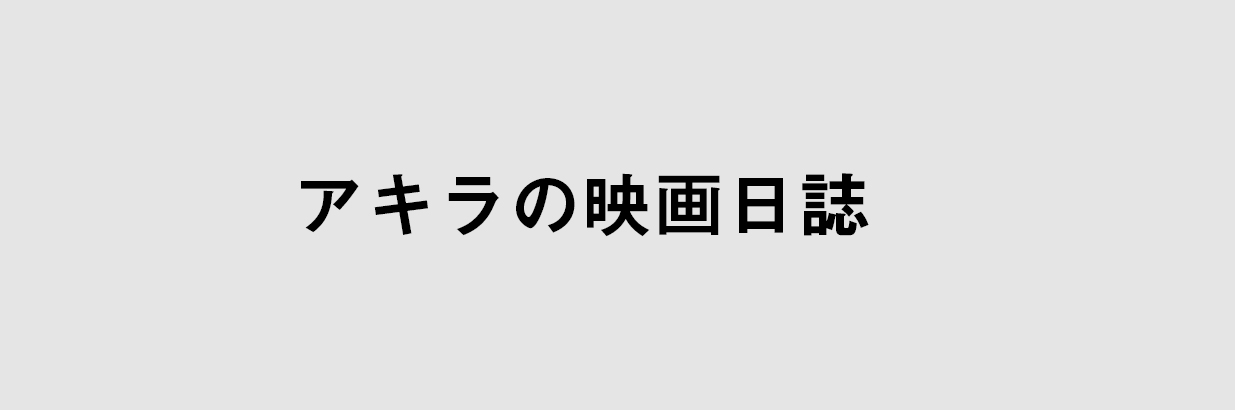
ブログ
2022/06/27
映画製作から六十年を経た今も色褪せず、瑞々しさを失わない名作です。 オードリーヘプバーンはこの一作で「世界の恋人」になりました。端正なモノクロ画面を見る度に切なさのつのる作品でもあります。ローマを表敬訪問中の欧州の若き某国王女がひとり大使館を抜け出し、偶然出会ったアメリカ人記者と淡い恋に陥る24時間の物語です。アン王女を演じたオードリーのスクリーンを圧倒する輝きが素晴らしく、気品溢れる仕草や誰をも魅了せずにはおかないチャーミングな笑顔と相まって、正に本物の王女がそこにいるかのようです。監督は名匠ウィリアムワイラー。 冒頭、侍従たちを従えたアン王女は真っ白なロングドレスで登場し、各国大使と謁見するのですが、その最中に足首が痒くなってしまい、片方の靴がドレスの中で脱げてしまいます。にこやかな微笑で次々と挨拶を交わしながらドレスの中は大忙し、何とか元通りに靴をはこうと奮闘するその可笑しさ、ワイラーはこの短いシーンで美貌の王女のお転婆ぶり、その愛すべき性格、そして彼女の置かれた立場を上品なユーモアを交えて的確に観客に伝えます。正に職人芸です。 又、王女に身分を隠したまま、一日を共にするアメリカ人記者ブラドリーを演じたグレゴリーペックも素晴らしい好演でオードリーを支え、この作品を単なるお伽話にはしていません。二人が大騒ぎしながら駆け巡る50年代のローマの名所旧蹟の数々も魅力的で大きな見所です。 私はこの映画を見る度に漱石の「坊っちゃん」を思い出します。国も時代も表現形式も全て違いますが本質的構造は一緒です。純粋な魂を持った主人公が異文化の地で大暴れして再び元の地に還る物語です。そして、祭りが華やかで、賑やかであればある程、その後に訪れる静寂の余韻は深いものです。 無鉄砲が過ぎて両親からさえも愛想を尽かされた坊っちゃんですが、清(きよ)という下女のおばあさんだけが「あなたは真っ直ぐでいいご気性だ」と、かばい抜きます。坊ちゃんが先生になって東京を発つ時も、駅頭でたったひとり涙ながらに見送ってくれます。四国へ渡った坊っちゃんは個性溢れる面々を相手に大暴れして帰京し、清と二人、暮らし始めるのですが、清はすぐ死んでしまいます。「後生だから坊っちゃんのお寺に」と云う清の頼みを聞いて、この痛快青春小説は「だから清の墓は小日向(おびなた)の養源寺にある。」という何とも云えない森閑とした結びで終わります。 ローマ市内を駆け巡った二人の大騒ぎの一日が終わり、淡い恋心を振り切った王女は自らの義務と責任を果たすべく、大使館へ戻ります。 舞台は再び大理石とシャンデリア煌く壮麗な謁見の間に戻ります。大勢の侍従と大広間一杯の世界中の報道陣に囲まれた中、最前列にいるブラドリーを見つけた瞬間、彼女は全てを悟ります。各国報道陣から質問が飛びます。「いくつもの国を歴訪されましたが、どの都市が一番お気に召しましたか?」王女はセオリー通り「いずれの都市もそれぞれに・・」と答えようとして瞬間、言い直します「ローマです!もちろんローマです!」「私はこの町の思い出をいつまでも懐かしむでしょう」侍従たちは予想外の王女の返答に驚き、顔を見合わせます。二人は他の人に気づかれないよう微かに微笑みながら、潤んだ瞳と瞳で最後のお別れを交わします。 この大人数での最後の謁見シーンに於ける会話の切り返しと映画的間の取り方は実に素晴らしく、W・ワイラーの名人芸でこの作品の全てのエッセンスがこの数分間に収斂されています。それは、互いにほのかな思いを抱いたブラドリーとアン王女がそれぞれの人生に於いてもう二度と言葉を交わすことも、出逢う事もないだろうという予感をこの二人と共に、見ている観客全員が理解する哀しみでもあります。 そして、アン王女と共に、観ている私たちも、いつまでもこの物語の思い出を懐かしむだろうという切ない予感でもあります。大勢の侍者に囲まれて王女が去り、全ての報道陣が去った後、ひとり残ったブラドリーは大広間の両端に侍従たちが控える中、ゆっくり出口まで歩いて行って、一度だけ壮麗な謁見の間を振り返ります。勿論、そこにはもう王女の姿はなく、静謐な空間があるだけです。この映画を見る度に私たちはブラドリーと共にアン王女の去った後の空間を振り返ります。まるで、遠い彼方に過ぎ去った自分自身のほろ苦い青春の残影をそこに探すかのように・・・ 静かに流れるテーマ曲と共にブラドリーの靴音だけが響いて映画は終わります。原案はダルトン・トランボですが、彼は50年代のハリウッドの赤狩り(red hunting)に遇って名前を出すことが出来ず、実際にネームクレジットされたのは57年後の2011年でした。 アン王女役のオードリーが余りにも気品高く、愛らしく、毅然とした美貌で圧倒的な存在だった為、撮影途中からスタッフ全員が正に本物の王女に接するかのようにオードリーの前で礼を尽くしたとも、最後の謁見の間の撮影が終わった瞬間、その場にいた大勢のイタリア人エキストラ全員が泣き崩れたとも伝えられています。