

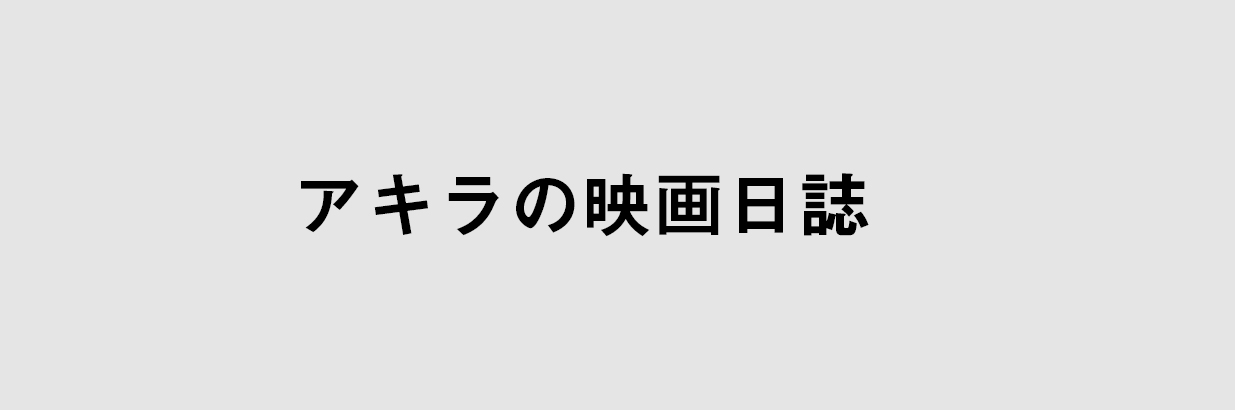
ブログ
2024/02/19
道化(王に)おお、おいたわしや、王様には裏切られなさったと!して、一体、誰方にでございます?
「されどわれらが日々」1964 柴田 翔
1960年(昭和35年)、戦後の日本とアメリカは「日米安全保障条約」を結びましたが、これに反撥して国内では「安保闘争」が始まりました。闘争の主体となったのは全国の大学生でした。
60年代半ばに入り、アメリカは泥沼のベトナム戦争に突入します。戦争は10年続き、数百万人が亡くなりました。それに伴い、反戦運動も世界的拡がりを見せ始めます。一方、日本では高度経済成長と相俟って戦後サブカルチャーの華が一気に開き、映画・演劇・芸術・漫画に至るまでかつてない斬新な地平が切り開かれました。国中が沸き立つような高揚感の日々が続き、それは永遠に続くかのようにさえ思えました。
一方、学生運動は先鋭の度合いを深め、60年代後半に入ると学生自治による大学バリケード封鎖が始まります。今では想像もつきませんが、近畿地方にある大学で私の先輩はバリケード封鎖に参加し、大学構内に立てこもり、意を同じくする学生達と共に日本刀を抜いて機動隊を迎えたと聞きました。手を焼いた大学当局による機動隊の学内導入、市中での学生と機動隊との数千人規模の乱闘が続き、内戦かと見まごうばかりの光景が現出しました。
この作品は1969年5月のものです。この年の1月には大勢の学生が立て籠った学生運動の一大拠点であり、象徴でもあった東大安田講堂が多数の機動隊の手によって陥落し、その状況は一日中TV中継されました。全国民が固唾を飲んでそれを見守りました。その日、東大本郷周辺には3万人を超える野次馬が集まったと記録にあります。この作品はそんな騒然とした世相やひりひりする学生達の日常の中、奇跡的に撮影されたものです。
議論は「認識か行動か」に始まり、「革命とは」「芸術とは」「天皇とは」「エロスとは」と多岐に亘り、留まるところを知りません。瞠目すべきは最後まで変わらぬ三島先生の学生に対する丁寧で真摯な態度と首尾一貫したその発言の在り様です。この作品の後半に70代半ばの老人となった白髪の芥正彦が登場し、眼光炯々と鋭くインタビュアーに逆質問するシーンがありますが、50年余の歳月を経て尚、彼の裡では未だ討論が続いている事が分かります。当時、東大全共闘は左派の頂点、三島先生は右派の極北かと見られていました。
時には笑い声さえ交えながら、激しく続く2者の議論に結論はありませんが、50数年前、国内最高の学問の現場でこれだけの真剣な公開討論があった事実は、驚きでしかありません。議論の最後に三島先生は「諸君の熱情だけは信じる」と云われて900番教室を去って行かれます。
三島先生は前年度(1968年)の傑出したノーベル文学賞候補であり、戦後日本が生んだ天才作家として、世界的にその名声を欲しい儘にされました。特にその多様でエネルギーに溢れた数々の行動は当時の若者の絶大な支持を受け、正に時代のアイコンでした。
川端康成(1968年度ノーベル文学賞)は先生の最後の長編小説「豊饒の海」の帯にこう記しました。「私は奇跡に打たれたように感動し、驚喜した。このような比類を絶する傑作を成した三島君と私も同時代人である幸福を素直に祝福したい。ああ、よかったとただただ思ふ。三島君の絢爛の才能は、この作で危険なまでの激情に純粋昇華している。この新しい運命的な古典はおそらく国と時代と論評を超えて生きるであろう。」あのプライドの高い孤高の文豪川端康成が手放しで絶賛したのです。
16才で処女作「花ざかりの森」を上梓し、早熟の天才と呼ばれた先生の作品は短編~長編の傑作小説群、戯曲、論文、評論、対談、歌舞伎の台本、映画と非常なハイレベルで膨大な数に及び、更に自衛隊に入隊され、民兵組織「盾の会」まで結成されました。その短かった生涯を思うと信じられない集中、熱量、計り知れぬ影響力です。
戦後を代表する名女形であり、人間国宝であった中村歌右衛門に対し、圧倒的知識量で五分の対談をされたのは20代の時でした。時には編集者を前にノー原稿で口述筆記をされ、一本の作品に仕上げられました。その文体と文法の余りの完成度の高さに一言一句の修正も必要なかったと編集は驚嘆と共に書き遺しています。
当時80万部を売り上げ、若者たちの熱い支持を受けた雑誌「平凡パンチ」(表紙は津市出身の新進気鋭のイラストレーター大橋歩が描いた)1967年の「日本のミスターダンディ」読者投票で一位は三島由紀夫、二位以下に三船敏郎、石原裕次郎、加山雄三、長嶋茂雄と続きます。つまり、三島先生は当時の映画俳優や、プロスポーツ選手よりもダントツの人気を誇ったのです。
1970年11月、先生は陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地にて壮絶な最期を遂げられます。「昭和45年11月25日」という題の新書があります。これはその日、あなたはどこにいて、この事件に対して何を思ったかというインタビュー形式のドキュメント本です。登場するのは当時防衛庁長官だった中曾根康弘、警察庁長官後藤田正晴、自民党幹事長田中角栄を始めとする政界の人々、石原慎太郎、澁澤龍彦、村上春樹を始めとする文学界の人々、小澤征爾、横尾忠則を始めとする芸術界の人々、村松英子、鶴田浩二、勝新太郎、中村吉右衛門、坂東玉三郎を始めとする俳優、演劇界の人々等百数十人に及んでいます。先生の死が如何に日本のあらゆる分野のあらゆる世代の人々に衝撃を与えたかを如実に表しています。衝撃は国内に留まらず、全世界に拡がりました。
その後、ありとあらゆる人々が発言し、いわゆる三島本といわれるものは100冊以上出版されましたが、結局、先生の真意は謎のままです。その年の暮れから追悼集会「憂国忌」が開催され、それは50年経った今でも続いています。
私が初めて参加した年は約400名程の参加者で会場通路まで満席でした。「国体とは何か」というテーマでパネリスト諸氏の白熱の議論が展開しました。その中で、パネリストのひとりが「上御一人と命を賭けてそれに付き従う者一名いれば、それが国体である」と発言された時、会場が静まり返った事を覚えています。討論会終了後に登壇された村松英子さんの深い思いの籠った素晴らしいスピーチで、館内に静かな感動が拡がりました。会の最後に参加者全員が起立し、伴奏付きで「海ゆかば」を2度合唱しました。
そして、歌い終わると同時に400名全員が、ひとりの漏れ無く、実に自然に壇上の三島先生の遺影に向かって低頭されました。私は一番後ろの席でその一部始終を見ました。それは美しい光景でした。会が終わり、外へ出ると平河町はもう夕暮れ時でした。タクシーを拾う為に大通りへ向かって歩きながら、私は日本人である事の喜びをささやかに思いました。