

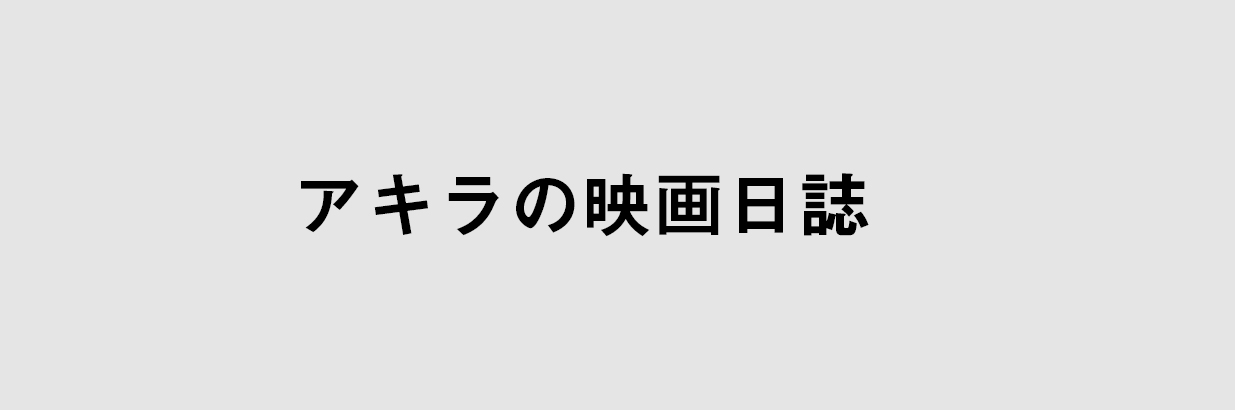
ブログ
2022/09/21
子供のころ、誰もが一度は夢見る、大空を自由に飛び廻りたいという夢を大人になっても忘れない人がいます。この作品の監督宮崎駿はその筆頭かも知れません。宮崎はその夢をアニメに、そして持てるダンディズムと粋の全てを主人公ポルコ・ロッソ(空の賞金稼ぎ、声・森山周一郎)に託しました。一見すると、魔法をかけられ豚の顔になった主人公の空の賞金稼ぎが、紺碧のアドリア海を舞台に大立ち回りする大冒険活劇に見えます。しかし、粋の体現者が豚の顔をしているという設定そのものがこの作品が単なる冒険活劇ではなく、一筋縄では行かない事を物語っています。 彼は自身の演出覚書きにこう書いています。「陽気だが、ランチキ騒ぎではなく、ダイナミックだが、破壊的ではない。誇りと自由に満ち、男たちはみんな陽気で快活だし、女たちは魅力にあふれ、人生を味わっている。」そして、「バカ騒ぎはつらい事を抱えているからだし、単純さは一皮むけて手に入れたものなのだ」と。この辺り、宮崎駿の制作に向かう姿勢と思想哲学がよく表れています。 舞台は地中海に面した陽光降り注ぐイタリア・アドリア海。時は第一次世界大戦後の1930年代。 離れ小島の楽園の如き隠れ家、岩陰の海面からポルコの愛機、真っ赤な「サボイアS.21飛行艇」がファっと飛び立つ瞬間の浮揚感。 低く垂れ込めたアドリア海の壮大な夕焼け雲を背景にゆっくり飛び続けるサボイア21の勇姿。 夕暮れの大海原を眼下に、愛するマダムジーナ(声・加藤登紀子)の酒場がある小島に旋回飛行しながら着水し、波濤の美しいループを描いて桟橋に愛機を着ける。 待っていた係留係にチップを渡し、葉巻に火を付け、マッチを海に捨てる。 この一連の流れるような描写の素晴らしさ。この間、BGMにはジーナが甘美に、低く歌う「LE TEMPS DES CERISES」 が流れ続けます。 この歌は単なる恋の歌ではなく、フランスの革命歌でここで宮崎は物語に二重の意味を持たせています。 又、日本でマダムと云えば夫人くらいの意味しかありませんが、欧州ではマダムの呼称は成熟した女性、女主人、或いは未亡人、深部にはキリストの母マリアの意を複雑に含んでいます。 歌声はポルコが店に入り、階段を降り、カウンターに着くまで流れ続けますが、階段を降りる極く短いシーンだけピアノソロに変化します。海面に投げ捨てたマッチがジュッという音を立てて海に消えるシーンといい、このピアノソロのシーンといい、計算され尽くした音響音楽構成になっています。 「可笑しいの、あのアメリカさん、私の顔見るなり結婚してくれだって」ポルコ、少し肩をすくめる。 「だから教えてあげたわ、私は3回飛行艇乗りと結婚したけど、ひとりは戦争で、ひとりは太平洋で、ひとりはアジアで死んだって」「分かったのか?」ジーナうなづく。 「今日、連絡があったの。ベンガルの奥地で残骸が見つかったって」ポルコ、首からナプキンを取り、ジーナに白ワインを注ぐ。「3年待ったわ。もう涙も枯れ果てた。」「良い奴は皆んな死ぬ。友よ。」透明な哀しみを湛えて静かに語る加藤登紀子の声、そして森山周一郎の渋い重低音の声が響き、名職人久石譲の哀切なヴァイオリンスコアが流れる中、二人、軽くグラスを掲げる。 ここまでの流麗な連続シーンに於いて、永く日本映画が描こうとしてかなわなかった仏蘭西映画の静謐とリリシズムが見事に結実しています。 「ここではお国(アメリカ)より、もう少し人生が複雑なの」大人が子供に諭すようにジーナが若きロナルドレーガンを想起させるカーチスにさらっと告げる時、「女は笑った。美人ではなかったが綺麗な女だった。癖のある髪をスカーフでぞんざいに纏め上げていたが、そのぞんざいさは実の所、相当な熟考を経た後のものだった」と、佐藤亜紀がその該博な西洋知識と美意識の全てを注ぎ込んだ傑作「バルタザールの遍歴」を思い出します。 ポルコの愛機は空賊たちの手によって破壊されてしまい、彼は新機制作の為、昔馴染みのミラノのピッコロ親父の工場へ赴きます。 戦時下、男は全員戦争に駆り出されてしまい、残った愛娘のフィオとおばさんやおばあさん達、女性陣のみで新飛行艇は建造されます。 フィォは宮崎作品共通の純潔の少女を象徴し、才能に秀れた、男勝りの美少女として登場します。 追手のファシスト警察の一群との銃撃戦の後、強力な新エンジンを積んだ真っ赤な新飛行艇が川面を巻き上げ、運河を遡り、橋をくぐり、強烈な水面バウンドを何度も繰り返しながら大空へ舞い上がる迄の場面展開は躍動感と高揚感に漲っています。 親友の手引きで危機を脱出した彼は空賊達の見守る中、宿敵カーチスと空中戦を戦い、勝利します。そして、駆け寄ったフィォが去り際にポルコにキスした瞬間、彼の顔が・・・。 この作品には飛行艇同士の銃撃シーンが何回も出てきますがポルコは相手の飛行艇を射撃するだけで、決して敵操縦士を直接撃ちません。 第2次世界大戦の前、戦いが未だ牧歌的匂いを残す最後の時代の物語です。 そして、ジーナに代表される母性、フィォに投影される少女聖性が作品全体を包み、その大きな包容力に包まれながら、賞金稼ぎの豚と髭面の空賊たち、ファシスト警察、イタリア空軍が思う存分、戦いを繰り広げる物語でもあります。 十方世界の無尽の天空と信じ込み、筋斗雲に乗って釈迦の掌の上で大暴れする孫悟空の一群のようなものです。 昔、「カッコイイってことは何てカッコワルイんだろう」と云った人がいましたが、この作品はその逆を行っているかのようです。 一見、とても単純そうに見えて、見方を転じると何層もの深い知識と痛みを伴った哲学が隠れている作品でもあります。 「ラストシーン、あの後、ポルコは人間に還ったのか、それとも豚のままなんでしょうか?」と問う記者の質問に宮崎はこう答えています。 「人間に戻るという事がそれほど大 事なことなんでしょうか?それが正しいと?」 「僕は豚が人間に戻るなんていう映画を作りたいとは全然思わない。それはもの凄くいやらしい映画になってしまう」 やはり、とても一筋縄ではいかない人物のようです。サイコーです。