

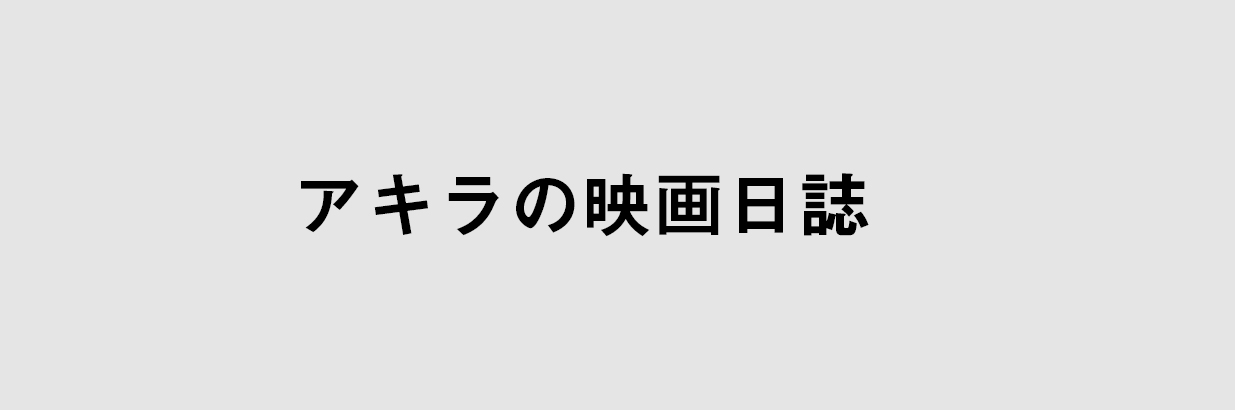
ブログ
2022/12/30
私が小さい頃、家の近所にはまだたくさんの原っぱや路地があり、至る所に遊び場がありました。とても空間が広かったのを憶えています。町内の家々は全て簡素な木造建築でした。夕暮れ時、十円玉を握りしめて路地を駆けて行くと自転車に乗った紙芝居のおじさんがやって来て、厚紙に描いたヒーロー物語を語り、その短い冒険譚に胸躍らせたものでした。携帯電話もパソコンも無く、TVさえ街頭にしかなかったのです。 それは未だ戦後間もない頃で、日本は貧しく、人々も人々の日々の暮らしも質素でつつましやかでした。しかしその反面、焼け跡から立ち上がった人間関係は今とは比べものにならないくらい濃密であらゆる場面で皆んな助け合って生きていました。 男はつらいよ」シリーズを見る度に、この頃の光景を思い出します。一九六九年の第一作から一九九五年の第四八作まで続くギネスシリーズです。どれ程多くの日本人が爆笑し、しんみりし、そして涙したか分かりません。第一作を超える第二作は無いというのが映画界の通説ですが、数少ない例外のひとつがこのシリーズです。愚兄賢妹の物語。ここには私共庶民の日々の暮らし、喜怒哀楽の全てがあります。東京下町のダンゴ屋とその裏にある小さな印刷屋を舞台に繰り広げられる泣き笑いの人間模様、その日常、その空気感、義理人情、見ず知らずの人に対する思いやり、どうしようもない切ない想いと現実、全てを言葉では説明できない、その溢れる哀感の全てがまるで宝石箱のようにぎっしり詰まっています。 話は単純で、毎回フーテンの寅さんが旅から帰ってきては下町柴又を舞台に多彩なマドンナたちと恋をし、ひと騒ぎ起こし、失恋の痛みを抱えては又、風のように旅に出て行くというお話です。その単純な物語が何故、こんなにも長い間、無数の人々に愛され続けたのか?。それはこのシリーズに描かれ続けた「人間としての愛しさ」、そして「日本人としての懐かしさ」ではないかと思います。私達は、この作品で手を替え、品を替えながら繰り返し描かれる日々の庶民の暮らし、そこに生まれる種々の哀歓、そしてその延長線上にある「日本人としての懐かしさ」に遂に抵抗できません。何故なら、その「哀歓」、「懐かしさ」はスクリーンの中にあるだけではなく、観客である自分自身の裡にあるからではないでしょうか? このシリーズは監督脚本の山田洋次を始め、一流のスタッフが集結し、全ての細部に至るまでとても丁寧に、巧みに作られています。 出演者も天才渥美清に始まり、妹さくら役の倍賞千恵子を筆頭に団子屋のおいちゃん(森川信)、おばちゃん(三崎千恵子)、博さん(前田吟)、印刷屋のタコ社長(太宰久雄)を始め、実に達者な役者陣で占められ、それはもう、実の家族親族ではないかとさえ思われる程です。 その時々のマドンナ、色とりどりのゲストの面々も、いかにもこんな人いるよなぁというはまり役のオンパレードです。 シリーズ中、素晴らしい作品は多々ありますが、私が忘れられないのは、小津安二郎以来伝統の松竹大船へのオマージュとリスペクトに溢れた第八作「寅次郎恋歌」です。マドンナ貴子さん(池内淳子)に恋をし、己の無力さに傷ついた寅さんがそれでも微かな期待を胸に秋の夜ひとり、貴子さんの家を訪ねるのですが・・・。小さな家、小さな庭いっぱいに咲き乱れる草花、夜空に満月、鳴きやまぬ虫の音、そして縁側に腰掛けた寅さんの口跡鮮やかな独白。 「たとえば、夕暮れ時、田舎のあぜ道を一人で歩いてたんですね・・・。ちょうど、りんどうの花がいっぱい農家の庭に咲きこぼれて、電灯はあかあかと灯って、その下で親子が水入らずの晩飯を食ってるんです。そんな姿を垣根越しに見た時に、ああ、これが本当の人間の生活じゃねえかなあ・・・フッとそんなこと思ったりしましてね・・・」 奥の部屋で電話が鳴って貴子さんが席をはずす。戻ってみると縁側の寅さんはもういない。小さな裏木戸だけが夜風にパタンパタンと揺れている。「寅さん」シリーズのというより、漂泊者の哀しみ漂う情感に満ちた日本映画屈指の名場面だと思います。名優渥美清逝って二四年、少しばかりの、ささやかな追悼文を書いてみました。